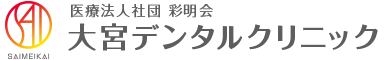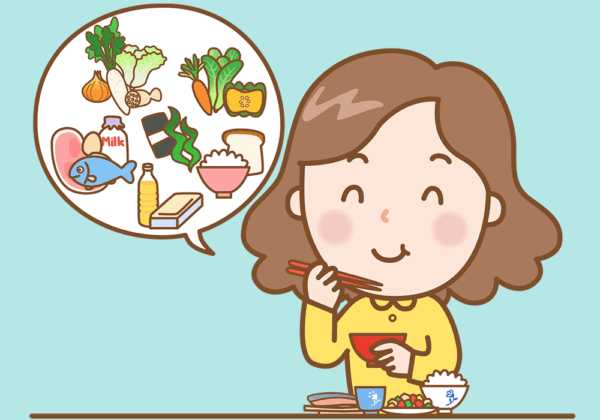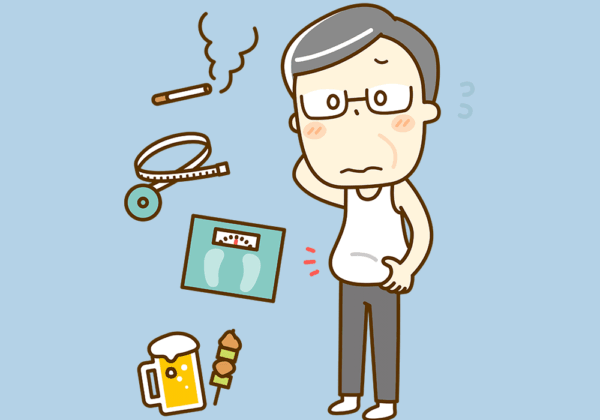歯の神経を抜くのはどんな場合?原因と注意点

こんにちは。 大宮デンタルクリニックです。
皆さまは歯科医院で「歯の神経をとる治療をします」「神経はとらなくて大丈夫ですよ」と言われたことはありませんか。
今回は「歯の神経をとる」とはどういうことなのか、歯の神経をとらなければならない場合や、とったあとの注意点についてお話しします。
「歯の神経をとる・抜く」とは?
歯の神経は「歯髄(しずい)」という組織のことです。歯髄は歯に水分や栄養、酸素などを送り込んだり、歯の強度を保ったりする役割があります。
虫歯ができて進行すると細菌が歯髄までおよび、激しい痛みや頬の腫れを引き起こします。
そのまま放置しておくと、最終的には歯を抜かなければならなくなることもあるため、感染した歯は神経を徹底的に殺菌・除去する治療が必要になります。
「神経をとる・抜く」とは、この歯髄をとり除くことであり、「根管治療」と呼ばれます。
歯の神経をとるのはどんなとき?
大きな虫歯ができたとき
重度の虫歯によって激しい痛みなどの症状があり、通常の治療で回復が難しい場合には、歯の神経をとる根管治療を行います。
歯が大きく欠けたとき
転んだり、スポーツなどで歯が大きく欠けたり、ヒビが入ってしまい、それが歯の神経にまでおよんでいる場合は、神経をとる根管治療を行います。
歯周病が進行したとき
歯周病が進行して歯を支えている骨が失われると、根の先から細菌が入って歯が痛くなるため、神経をとる根管治療が必要です。
ブリッジ治療などが必要になったとき
抜歯が必要な場合、その部分を補う方法の一つとして「ブリッジ治療」があります。ブリッジ治療をする場合、欠損した歯の前後を大きく削る必要があるため、治療後にしみたり痛みが出ないよう、あらかじめ神経をとることが多いです。
知覚過敏の症状が治らないとき
知覚過敏とは、虫歯がなくても冷水や空気などで、ツーンとした強いしみる感覚が起こる状態になります。
通常、薬液塗布や知覚過敏用の歯磨き剤の使用で改善されることが多いですが、重篤な場合は神経をとることもあります。
歯の神経をとった場合に気を付けること
歯の神経をとると痛みはなくなりますが、歯に栄養や水分が行き渡らなくなり、歯は死んだ状態となります。死んだ歯は次第に乾燥し、割れやすくなります。根の先まで割れたりヒビが入った場合は抜歯しなければなりません。
また神経をとると痛みを感じないため、虫歯になっても気づかずに進行してしまうことが多いです。そのため、定期的に歯科検診を受けて、虫歯になっていないかチェックしてもらいましょう。
まとめ
歯の神経をとると、痛みはなくなりますが、歯の寿命は短くなり、将来的に歯を失うリスクが高くなります。
そのため、虫歯や知覚過敏はできるだけ早く治療することが大切です。
また、神経をとった歯は治療を最後までしっかり受けることが重要で、治療後も半年〜1年に1回の定期検診を受けて、歯の状態を確認することをおすすめします。
当院では、患者さんの歯とお口の健康を守るため、定期的な歯科検診を行なっています。治療後の状態確認や磨き残しのチェックを丁寧に行い、必要に応じて適切なアドバイスも行なっています。安心して長く健康な歯を保つために、ぜひ定期的なご来院をご検討ください。
初診WEB予約
お気軽にお問い合わせください。